「IPA」ってなに? 情報処理推進機構とはどんなもの?〜ITを支えるチームの話〜
なつめ ライフハック

ニュースやネット記事を読んでいると、「IPA」って言葉を見かけたことはありませんか?
「なんかITとかセキュリティの話題でよく出てくるなぁ」くらいに思っていた方もいるかもしれません。
実はこのIPA、私たちのデジタル社会を陰でしっかり支えてくれている、頼れる存在なんです。
今回は、そんなIPAがどんなものなのか、どんなことをしているのか紹介していきます。
IPAってどんな団体?
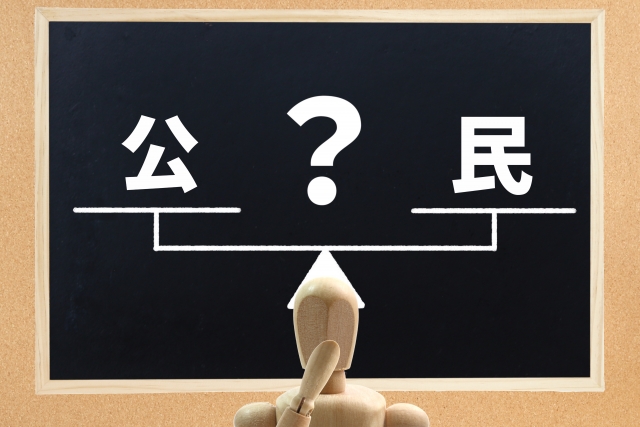
すごく簡単に言うと、IPAは「ITのために頑張っている団体」です。
もう少し具体的に言えば、「みんながITを安全に、便利に使えるようにするために活動している、国の専門チーム」といったところでしょうか。
たとえば、スマホやパソコンを使っていて困ったことが起きないようにしたり、新しい技術が安心して使えるようにしたり。そんな“デジタル社会の頼れるパートナー”——言いかえれば、そっと支えてくれるチームのような存在です。
ちなみに「IPA」というのは「独立行政法人 情報処理推進機構」という正式名称の略で、英語では「Information-technology Promotion Agency, Japan」と言います。長いですね。
発音の仕方は「IPA(アイピーエー)」、イギリス発祥のビールと同じ呼び方です。「アイパ」ではないですよ。
「独立行政法人」というのは、国の仕事をサポートするために作られたチームで、ある程度自由に専門的な活動ができるのが特徴です。つまり、民間とは違うけれど、役所とも違う。国と民間の間でうまく調整する役割をもっています。
IPAもまさにその一つで、社会や企業、そして技術のあいだをつなぐ“橋渡し役”として、IT社会全体を支える存在でもあります。
どんなことしてるの?
ここまでで、IPAが「ITを支えるチーム」だということは、なんとなく伝わったでしょうか?
では、そんなIPAが実際にどんな活動をしているのか、もう少し具体的に見ていきましょう。
現在、IPAは3つの大きな柱を中心に、さまざまな取り組みを進めています。それぞれ紹介していきますね。
1. デジタル基盤の提供

たとえば、便利なサービスやアプリを作るには、共通のルールや仕組みがあるとスムーズですよね。
IPAは、そうした「土台づくり」を担当しています。具体的には、
-
🟨社会全体の仕組み(Society 5.0)に合うITの設計
→ みんなが使いやすいITの仕組みを考える -
🟨インフラやデータのルール作り(標準化・統一化)
→ デジタルの道具やルールをそろえて分かりやすくする -
🟨いろんな企業や団体が使える仕組みの提供
→ いろんな会社やグループが一緒に使えるようにする
などを、国や企業と連携しながら整えています。
まるで、みんなが通れる“情報の高速道路”を整備する人たちのような存在です。
2. デジタル人材の育成

デジタルの世界がどんどん進む今、それを支える人がとっても大事なんです。
IPAは、
-
🟨情報処理技術者試験の運営
→ ITにくわしい人を育てるための国家試験を実施 -
🟨ITやセキュリティに関する教材や研修の提供
→ デジタルの勉強ができる教材や講座を用意 -
🟨デジタル人材向けの評価(アセスメント)の仕組みづくり
→ デジタルのスキルをきちんと測るしくみを考える
などを通じて、未来のIT人材を育てる“教育チーム”としても活動しています。
3. サイバーセキュリティの確保

最近は、ネットのトラブルが私たちの生活にも直接影響するようになってきました。
IPAはこれまで、
- 🟨ウイルスや詐欺サイトへの注意喚起
→ 「あやしいサイトに注意して!」といったお知らせ - 🟨トラブル発生時の情報提供や対処法
→ 困ったときに「どうすればいいか?」を教えてくれる
など、「何か起きたときの対応」に力を入れてきました。
でも最近では、
- 🟨サイバー攻撃の“意図”を読み解く力
→ 「どうして狙われたのか?」を事前に見抜く - 🟨システム設計の段階から安全を考える(「セキュリティバイデザイン」という考え方だそうです)
→ 最初から安全な作りにする
といった、「“起きる前に守る”ための取り組み」も始まっています。
つまり、セキュリティの未来を見据える“予防医”のような存在なのです。
💡ちなみに、IPAのセキュリティ情報を活用して、このブログでも何度か記事を書かせていただいています!
🔗【2025年版】個人が注意すべき情報セキュリティ10大脅威
🔗「知らなかった…」では済まされない!2025年の情報セキュリティ10大脅威まとめ
🔗家庭や職場で見直そう!2月は「サイバーセキュリティ月間」
その他の活動も充実しています

この3つの柱のほかにも、IPAはさまざまな取り組みをしています。
- 🟩地域や中小企業向けのデジタル支援
→ ITにくわしくない企業や地域のサポート - 🟩新しい技術に関する国際ルールづくりへの参加
→ 世界での「きまりづくり」にも関わっている - 🟩社会課題に合わせたシステム設計支援
→ 困りごとを解決する仕組みを一緒に考える
など、「今の課題」と「これからの社会」に目を向けた活動が進められています。
つなぎ手としてのIPA

IPAは、技術を開発する企業でもなければ、ルールを作る政府そのものでもありません。
でもその間で、
- ルールをわかりやすく整理したり
- 新しい仕組みをうまく使えるようにしたり
- 人と人、システムと社会を結びつけたり
と、いろんな立場の人たちを支える“つなぎ手”としての役割を果たしています。
もし次にニュースで「IPAが発表しました」「IPAが注意喚起を出しました」といった言葉を見かけたら、
「“ITの調整役でつなぎ手のチーム”だ」と、ふわっと思い出してもらえたら、ニュースの内容がより理解しやすく感じられるかもしれません。
この記事を読んで、少しでもITを身近に感じてもらえたなら、それだけで今日のおやつが3割増しでおいしく感じそうです。
ちょっと気になったかも?と思った方は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の公式サイトも、よければのぞいてみてくださいね。




