マイナンバーカードの“保険証廃止”はいつ?中小企業への影響を整理
さき 時事ネタ
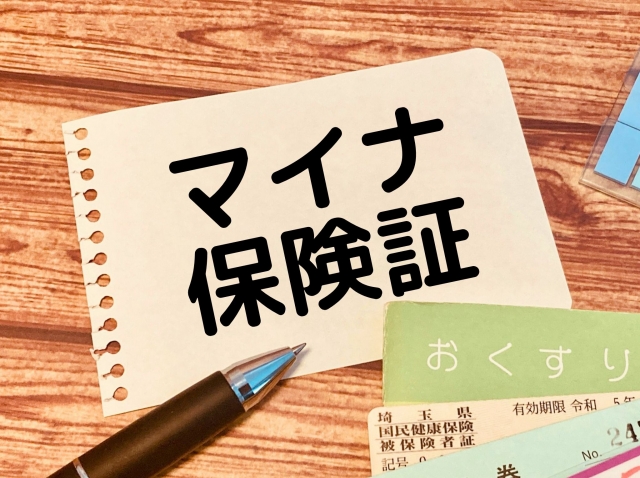
「健康保険証がなくなるらしい」「マイナンバーカードに一本化されるって本当?」——そんな声を最近よく耳にします。
政府は医療のデジタル化を進める一環として、これまでの健康保険証を廃止し、「マイナ保険証」への移行を進めています。
とはいえ、時期や手続きの変更点など、まだ少しわかりにくい部分も多いですよね。この記事では、健康保険証の廃止時期や背景、そして中小企業や働く人への影響を、やさしく整理してお伝えします。
1. 健康保険証はいつ廃止されるの?
現在使われている健康保険証は、2025年秋に廃止予定です。
すでに2024年12月をもって、新しい健康保険証の発行は終了することが決まっています。
つまり、2025年秋以降は、原則としてすべての医療機関で「マイナンバーカード」を健康保険証として使う形になります。これがいわゆる「マイナ保険証」です。
ただし、「まだマイナンバーカードを持っていない」「カードをなくしてしまった」という人のために、当面は代わりに使える『資格確認書』が発行される予定です。
● まとめると
- 2024年12月:健康保険証の新規発行が終了
- 2025年秋:既存の保険証の使用も終了(完全移行)
- カード未所持者には「資格確認書」を発行
2. そもそもマイナ保険証ってなに?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードに健康保険証の機能をひも付けたものです。
医療機関や薬局でカードを専用の機械にかざすだけで、保険資格の確認ができるようになります。
さらに、本人が同意すれば、過去の薬の履歴や特定健診の情報も確認できるため、医師がより正確な診療を行いやすくなるというメリットもあります。
● マイナ保険証を使うメリット
- 保険証を持ち歩く必要がなくなる
- 転職・引っ越し時の手続きがスムーズになる
- 医療情報を一元管理できる
- 医療費控除などの申請もオンラインで簡単に
ただし、医療機関によってはまだマイナ保険証に対応していないところもあり、完全に浸透するまでには少し時間がかかりそうです。
3. 中小企業への影響は?
会社で健康保険に加入している場合、これまで「健康保険証が届いたら社員に配布する」という流れでした。
しかし今後は、その発行がなくなり、各社員が自分のマイナンバーカードを保険証として使うことになります。
つまり、企業の総務・人事担当者には、これまでとは少し違う対応が求められます。
● 主な変化・注意点
- 新入社員や退職者の保険証発行・返却の手続きが不要になる
- マイナンバーカードを持たない社員には「資格確認書」対応が必要
- 従業員からの問い合わせが増える可能性がある
- 社内でマイナンバーを扱う機会が増えるため、情報管理の徹底が必要
たとえば「マイナカードがうまく読み取れない」「資格確認書ってどうやって使うの?」といった質問が、社員から寄せられるケースも考えられます。
企業としては、あらかじめ制度を理解し、従業員に分かりやすく説明できる体制を整えておくことが大切です。
4. 今からできる準備
まだ少し先の話と思われがちですが、2025年秋はあっという間にやってきます。
混乱を防ぐためにも、今のうちから少しずつ準備を進めておきましょう。
● 企業ができること
- 社員にマイナンバーカード取得を呼びかける
- 健康保険組合・協会けんぽの最新情報を定期的にチェックする
- 就業規則や社内資料の「保険証」の表記を見直す
- 資格確認書の発行ルールを理解しておく
とくに「マイナンバーカードは申請してから届くまでに数週間かかる」ため、まだ持っていない社員には早めの申請を促すのがポイントです。
5. トラブルを防ぐために知っておきたいこと
マイナ保険証の導入初期には、カード読み取りエラーや資格情報の誤登録といったトラブルも報告されました。
最近はシステム改善が進んでいますが、完全にゼロとはいえません。
そのため、企業側も「トラブルが起きた場合は資格確認書を使えばOK」といった基本的な対応ルールを共有しておくと安心です。
また、マイナンバー関連情報を扱う機会が増えることから、個人情報の取り扱いにはいっそうの注意が必要です。社内での管理ルールを明文化しておきましょう。
6. まとめ:制度の変化に早めの理解と対応を

マイナンバーカードの保険証廃止は、いよいよ2025年秋に本格的に始まります。
国としては、医療DX(デジタル化)を進めるための大きなステップですが、現場の混乱を最小限にするためには、企業と従業員の両方が制度をしっかり理解することが大切です。
「まだ先の話」と思っているうちに、あっという間に切り替えの時期がやってきます。
いまから情報を集め、社内で周知しておくことで、スムーズに新制度へ対応できるはずです。
制度が変わっても、目的は“便利で安心な社会づくり”。
マイナンバーカードを上手に活用して、これからの働き方や暮らしをより快適にしていきたいですね。




