あの手口に名前があった!「ビッシング」と「スミッシング」、身近に潜む詐欺の正体
なつめ ライフハック
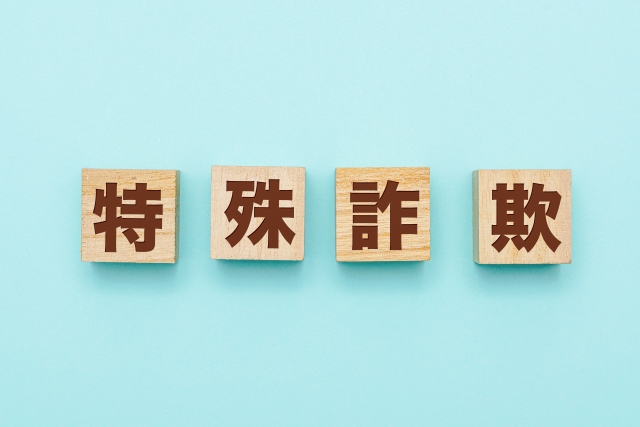
ニュースで「特殊詐欺が…」という言葉をよく見聞きしますよね。
スマホに知らない番号から電話がかかってきて、画面を見たら海外からっぽい番号だった…なんて経験をした方もいるかもしれません。
そんな「特殊詐欺」、奈良県ではどれくらい被害が出ているのか調べてみました。
奈良県警の発表によると、令和7年8月末までの特殊詐欺被害は214件、被害額は約14億850万円。さらにSNSを利用した投資・ロマンス詐欺の件数は117件、被害額は約14億6,550万円にのぼっています。※1
数字だけ見ても、詐欺が私たちの生活にとても身近な危険になっていることがわかります。
こうした詐欺はまとめて「フィッシング詐欺」と呼ばれることもありますが、実は手口によって細かく名前がついているのをご存知でしたか?
厳密には、フィッシングは銀行のログイン情報やクレジットカード番号といった個人情報を盗むための詐欺を指します。そして、その目的のために、様々な手段が使われています。
今回はその中から、特に注意すべき「スミッシング」「ビッシング」の手口について、身近な例を交えながらご紹介します。
スミッシング・ビッシングって、どう違うの?
詐欺の手口が多様化したことで、それぞれに名前がつけられました。まずは、意味を簡単に見てみましょう。
- ✉ スミッシング(Smishing)
SMS + Phishing(フィッシング) → Smishing
SMS(ショートメッセージ)を使ったフィッシング詐欺です。宅配業者や銀行を装った偽のメッセージで、偽サイトに誘導されます。 - 📞 ビッシング(Vishing)
Voice + Phishing(フィッシング) → Vishing
電話を使ったフィッシング詐欺です。銀行員や公的機関を名乗り、電話で暗証番号などの個人情報を聞き出そうとします。
つまり、詐欺の目的は同じでも、手段によって呼び方が変わるということなんですね。
ちなみに「フィッシング」という言葉は、英語でphishingと書きます。
この「phishing」という言葉は、“fishing(魚釣り)”と“sophisticated(洗練された)”を組み合わせて作られた造語だといわれています。※2
つづいて、電話やSMSで行われる詐欺の具体的な手口と、日常でできる対策を見ていきましょう。
スミッシング(SMS詐欺)

スミッシングは「SMS(ショートメッセージ)」と「フィッシング」を組み合わせた言葉です。SMSで偽のメッセージを送りつけ、個人情報を抜き取ろうとします。
よくある手口の例
- ⚠️ 宅配業者を装う
お荷物の再配達手続きをお願いします。こちらからご確認ください[偽サイトへのリンク] - ⚠️ ECサイトや銀行を装う
お客様のアカウントが凍結されました。ログインして情報を更新してください[偽サイトへのリンク] - ⚠️ 携帯電話会社や通信会社を装う
ご利用料金の確認ができません。支払いを完了してください[偽サイトへのリンク]
どれも本物そっくりで、リンクをクリックすると見分けがつかない偽サイトに誘導され、個人情報やクレジットカード情報を入力させられます。
スミッシングに引っかからないポイント
- ✅ 心当たりのないSMSは無視する
知らない番号や身に覚えのない内容のSMSは、無視するのが安全です。 - ✅ リンクは絶対にクリックしない
本物に見えても、SMSに書かれたリンクはクリックしないでください。 - ✅ 自分で公式サイトを探してアクセスする
確認が必要な場合は、SMSのリンクではなく、自分でブラウザを開いて公式サイトを検索してアクセスする習慣をつけましょう。
ビッシング(電話詐欺)

ビッシングは「ボイス(声)」と「フィッシング」を組み合わせた言葉です。電話であなたを信じ込ませ、個人情報やお金をだまし取ろうとします。
よくある手口の例
- ⚠️ 銀行やクレジットカード会社を名乗る
「お客様の口座で不正な取引が確認されました。すぐに本人確認をするので、カード番号と暗証番号を教えてください。」 - ⚠️ 公的機関や大手企業などを名乗る
「未払い料金があります。このままだと法的措置を取ります。支払いのため、振込先情報をお伝えします。」
<AIによる新しい危険>
最近では、AIが本物の家族や知人の声を真似て、「声がそっくりな人」から「今すぐお金を振り込んで」と電話がかかるケースも報告されています。AIの音声合成技術を悪用したもので、見抜くのは非常に難しいです。
ビッシングに引っかからないポイント
- ✅ 電話で個人情報を教えない
銀行や公的機関が電話で暗証番号やパスワードを聞くことはありません。聞かれても答えないようにしましょう。 - ✅ 一度電話を切って自分でかけ直す
不審な電話がかかってきたら、まず電話を切ります。その後、公式サイトや電話帳に載っている番号に自分でかけ直して確認しましょう。相手が教えた番号にかけ直すのは避けてください。 - ✅ 家族や友人と合言葉を決めておく
AIによる声のなりすましが心配な場合、家族や友人と電話用の合言葉を決めておくと安心です。
知っていれば安心!
スミッシングもビッシングも、私たちを焦らせたり不安にさせたりする心理的なワナが使われています。でも、手口を「知っている」だけで、多くの詐欺は防げます。
今日から意識したいのは、この2つです。
- 📍 SMSが来たら「リンクはクリックせず、自分で公式サイトを探す」
- 📍 電話が来たら「一旦切って自分でかけ直す」
どちらの詐欺も気をつけることは、すぐに反応しないことです。
とはいえ、相手に急かされると、冷静な判断が難しくなってしまうかもしれません。
そんなときは、「数分だけ別のことをしてみる」のがおすすめです。深呼吸をして気持ちを落ち着けるのも効果的です。
また、「誰かに話して相談してみる」のも良い方法です。自分だけで抱え込まず声に出すことで、気持ちを整理し、落ち着いて判断できるようになります。
“あれ?これ怪しいかも?”と気づけたら、もう半分は勝ちですよ。
—
出典:
※1 奈良県警察ホームページ 「令和7年8月末 奈良県内刑法犯認知件数【暫定値】について」
※2 総務省『国民のためのサイバーセキュリティサイト』「フィッシング詐欺とは?」
(本記事の記載内容は、上記資料を基に筆者が要約・編集したものです。)
—




